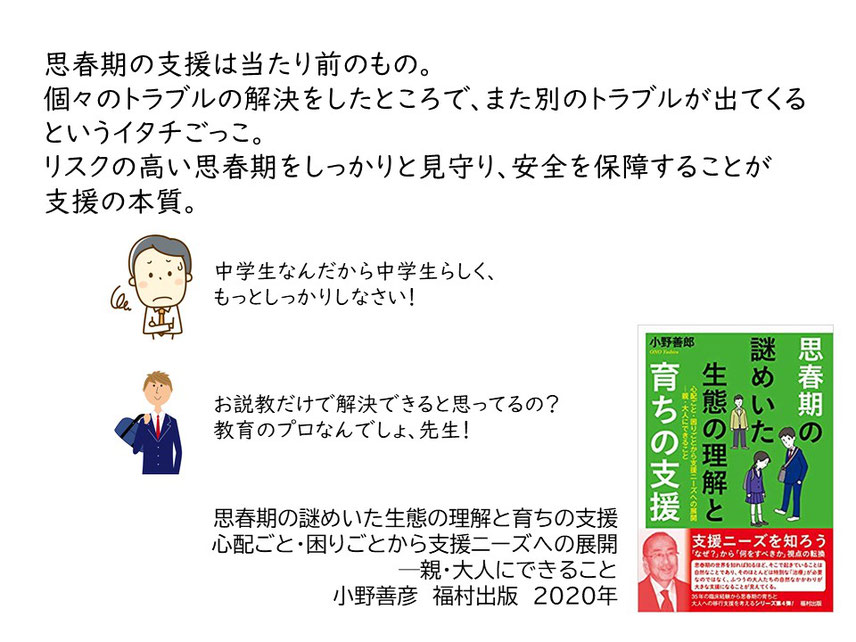
思春期の謎めいた生態の理解と育ちの支援 心配ごと・困りごとから支援ニーズへの展開 ―親・大人にできること
小野善彦 福村出版 2020年
24 思春期の生態系の中での成長は、多様な相互作用が反応炉の中で化学反応を起こすようなもので、その反応を親や大人が直接的にコントロールをすることはできない。
28 社会性の本質は対人関係
「ひきこもり」・・・家から出るかどうかよりも、他者との関係の有無が重要
48 もともと思春期は何かと問題が顕在化してくる時期
→本来の思春期の問題なのか、学校適応や学力のような学校の問題なのかごちゃごちゃに
76 外在的問題行動・・・攻撃的行動、非行、多動、かんしゃく
内在的問題行動・・・不安、抑うつ、ひきこもり、不登校
80 再登校にこだわらない
具体的な目標が見えなくなり、思春期本来の違いや悩みに直面することで、本人の苦悩が深まることもある。
89 「問題行動」はまさに大人の視点から見た思春期の具体的な形
102 実際の思春期の心配ごとや困りごとの多くは、親や学校が「ふつう」と思っている行動からの逸脱
104 同じ年齢集団の平均的な特徴・・・「定型(typical)」
「ふつう」を専門的にいうと「定型」
122 子どもの意欲や能力と環境が求める要求や期待とがうまくマッチしている→適応的な行動
ミスマッチ→不適応的な行動、問題行動
139 子どもの要求どおりにしないと支援もある
↓
子どもにかかわることが支援の本質
かかわりが求められるきっかけになるのが支援ニーズ
141 ある程度の当たりを付けることはできるが、それはあくまでも仮説であって、真のニーズではない
142 思春期の支援は当たり前のもの
↓
個々のトラブルの解決をしたところで、また別のトラブルが出てくるというイタチごっこ
↓
リスクの高い思春期をしっかりと見守り、安全を保障することが支援の本質
151 思春期の育ちの支援
誰にでもできるごく自然なものから、より専門的で介入的なものまでの連続体
175 思春期外来
治療を要する程度の精神疾患と診断されたのは約5%程度